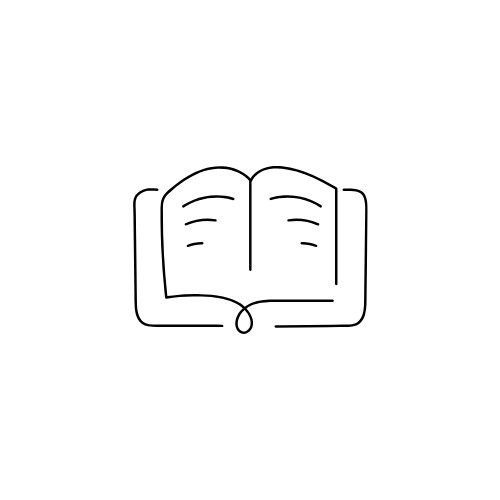応用情報技術者試験の勉強をしていて、「HDD」「DRAM」「フラッシュメモリ」など、いろんな用語が出てきました。
正直、「何が違うの?」「それぞれどこに使われてるの?」と混乱したので、自分なりに整理してみました。
同じように悩んでいる人の参考になればうれしいです!
【図解】記憶装置の分類と用途

こちらはよくある記憶装置の分類わけです
記憶装置には大きく揮発性(電源を切ったら消えるもの)と不揮発性(電源を切っても消えないもの)があります
以降でそれぞれについてまとめます
各メモリの特徴と使われる場所
HDD:大容量ストレージ(磁気記憶)
- 不揮発性。電源を切っても消えない
- 遅いけど安い
- 【使われてる場所】PCのストレージ(古いPC・外付けHDDなど)
DRAM:メインメモリ(電荷方式)
- 揮発性
- 高速だがリフレッシュが必要
- 【使われてる場所】マザーボードのRAMスロット(DDR4など)
SRAM:CPUキャッシュ(フリップフロップ方式)
- 揮発性
- 超高速だけど高価
- 【使われてる場所】CPU内部のL1〜L3キャッシュ
フラッシュメモリ:SSDやUSB(電界効果)
- 不揮発性。書き換え可能
- 書き込み寿命はあるけど、普段使いには十分
- 【使われてる場所】SSD、USB、スマホのストレージ
つまづいたポイント
DRAMやSRAMが何に使われているかわからずイメージできなかった
DRAMやSRAM、フラッシュメモリを文字だけ見ていると実際に何に使われているのかをイメージできないため、なかなか覚えられませんでした。
何に使われているものなのかを知ることで特徴も含めて理解することができました。
どれが揮発性でどれが不揮発性なのか
これについては前述の何に使われているかを理解することで覚えることができました。
フラッシュメモリが揮発性か不揮発性かをただ覚えるのは個人的に大変でしたが、フラッシュメモリが、SSDやUSBメモリに使われていると分かれば、電源を消しても消えないものなので不揮発性だとわかります。
最後に
記憶装置に関する用語とそれぞれの用途をまとめました。
余裕があればフリップフロップ方式や電荷方式についても調べてみようと思います。